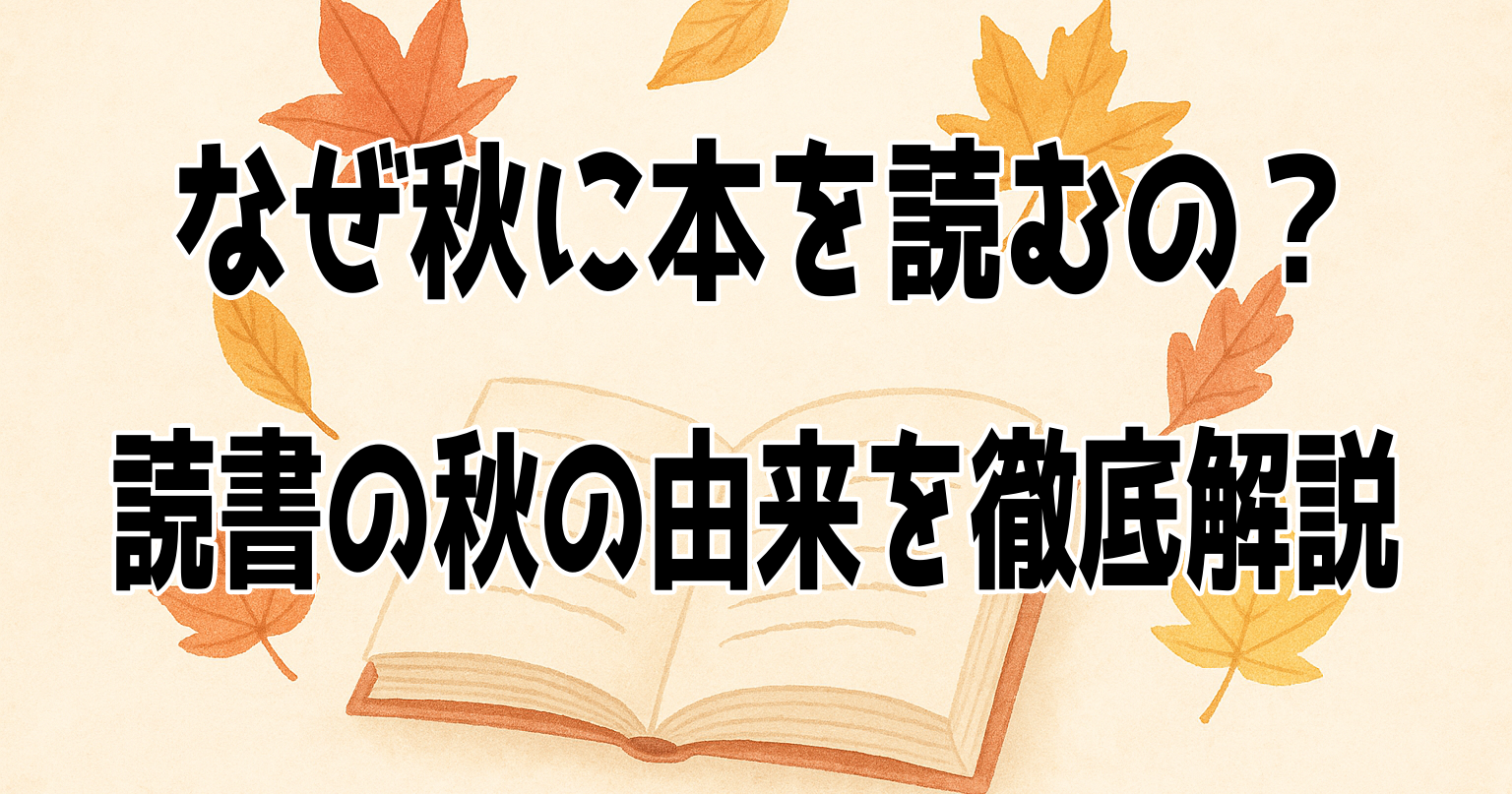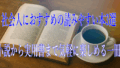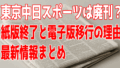「読書の秋」という言葉、よく耳にしますよね。紅葉の季節になると、なぜか本を開きたくなる…そんな気持ちになる方も多いんじゃないでしょうか。
でも、そもそもどうして秋に読書?なぜ春でも夏でもなく、秋なんだろう?そして「読書の秋」という言葉はいつから使われるようになったのか…。
実はそのルーツは、はるか昔の中国の詩にまでさかのぼります。さらに日本では、戦後に始まった「読書週間」が定着することで、今のように“秋=読書の季節”というイメージが広がっていったんです。
今回は、そんな「読書の秋」の由来や背景をじっくりひもときながら、10月や11月に行われる読書週間とのつながりまで紹介していきますね。
読書の秋の由来

「読書の秋」という言葉の源は、千年以上も昔の中国にさかのぼります。唐の時代の文人・韓愈(かんゆ)が詠んだ詩『符読書城南』に、「燈火稍可親(灯火、ようやく親しむべし)」という一節があるんです。
これは「秋になると涼しくなって夜も長くなり、灯りの下で本を読むのにちょうどいい季節だ」という意味。シンプルだけど、とても情景が浮かびますよね。静かな秋の夜、灯りに照らされた机の上で本を開く…その光景は、今の私たちにも自然に響いてきます。
この考え方はやがて日本にも伝わり、「秋は読書に向いている季節」という感覚として広まっていきました。特に有名なのは、夏目漱石の小説『三四郎』に「燈火親しむべし」が引用されていること。こうした文学的な引用がきっかけの一つとなって、近代以降「読書の秋」というフレーズが親しまれるようになったんです。
そして面白いのは、実は海外には「読書の秋」にぴったり対応する表現があまり見られないこと。英語圏ではむしろ「Summer Reading(夏の読書リスト)」という文化が一般的で、秋=読書と強く結びつけているのは日本ならではの特色なんです。だからこそ、このフレーズには独自の季節感があって、より魅力的に響くのかもしれませんね。
なぜ秋に読書なの?
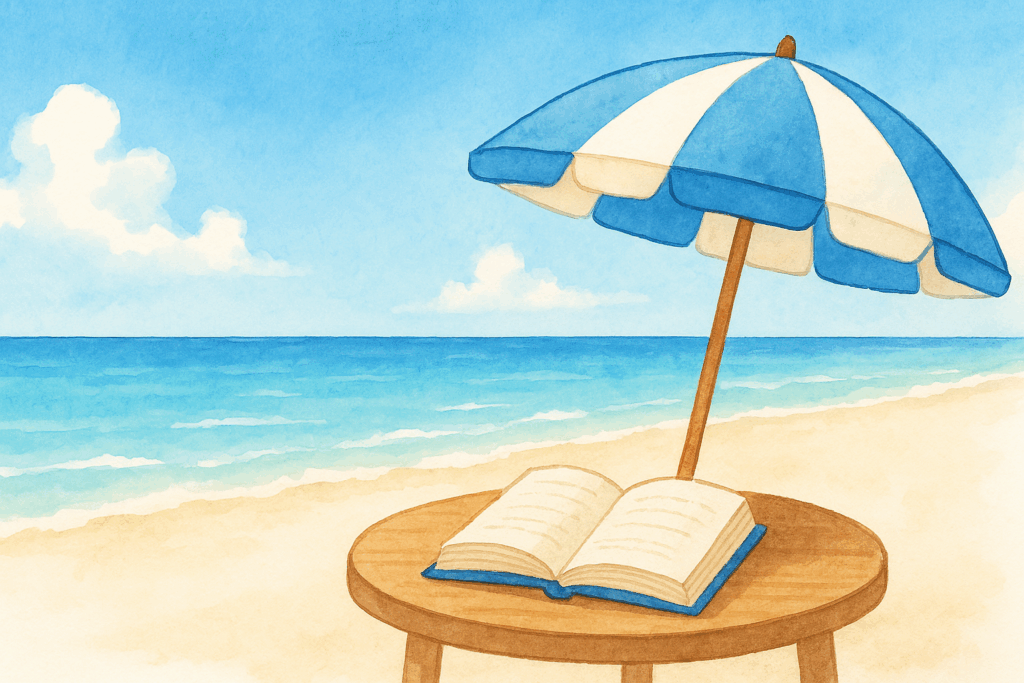
考えてみると、「春の読書」や「夏の読書」ってあまり耳にしませんよね。やっぱり「秋」だからこそ、しっくりくる理由があるんです。
まず一つは気候。夏の暑さがやわらぎ、冬の寒さもまだ厳しくない秋は、一年の中でも最も過ごしやすい時期。涼しい風が吹く中で、落ち着いて本を読むにはぴったりなんです。
そしてもう一つは夜の長さ。秋が深まるにつれて日が短くなり、自然と「夜の時間」が増えていきます。その分、家の中で静かに過ごす時間も長くなるので、灯りの下で読書する習慣が生まれやすかったんですね。
ちなみに、「◯◯の秋」という表現は読書だけではありません。「スポーツの秋」「食欲の秋」など、秋を楽しむキャッチコピーは戦後に新聞や雑誌、さらに行政のキャンペーンを通じて広まったと言われています。人々に「文化や健康を楽しもう」と呼びかける流れの中で、「読書の秋」も自然と定着していったんですね。
今も昔も、「秋=本を読むのに最適な季節」という感覚は変わらない。だから紅葉の季節になると、自然と本を開きたくなるのでしょうね。
読書の秋は何月?
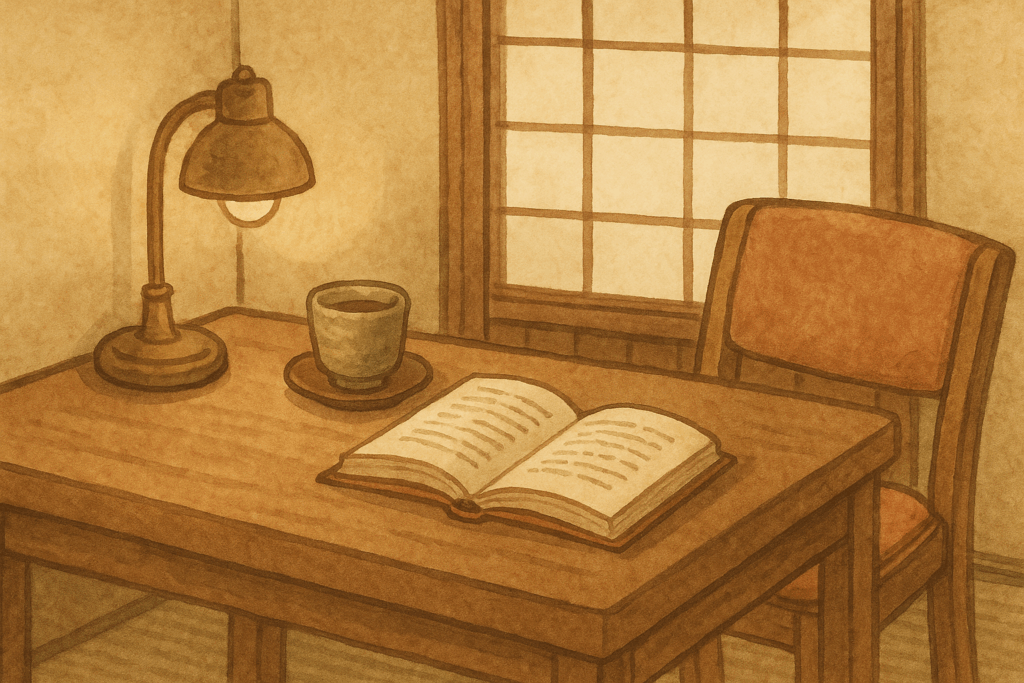
現代の日本で「読書の秋」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは10月から11月ごろ。
ちょうど紅葉が色づき始め、空気が澄んでくる、心地よい季節ですよね。
実際に日本では10月27日〜11月9日が「読書週間」と定められています。この2週間の真ん中にあるのが、文化の日(11月3日)。この日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」とされていて、読書週間のシンボルにもなっています。
さらに、初日の10月27日は「読書の日」。この日をきっかけに、本屋さんや図書館では関連イベントが開催され、秋の恒例行事として私たちに親しまれているんです。
🌿豆知識
実は「読書週間」が始まった1947年は、戦後の混乱期。物資も情報も不足していた中で、「心の糧として本を読もう」という願いが込められていたんです。だからこそ、今もこの習慣が続いていると知ると、ちょっと感慨深いですよね。
「読書の秋」はいつから広まったの?
「読書の秋」という言葉自体は昔からありましたが、今のように秋=読書のイメージが広く定着したのは戦後のこと。
きっかけは1947年の第1回「読書週間」です。当初は11月17日〜23日の1週間だけでしたが、翌年からは10月27日〜11月9日の2週間に拡大され、今もそのまま続いています。
毎年の恒例行事になったことで、「秋に本を読む」という習慣が一気に広まりました。
そして、この行事があるからこそ「秋=読書」という日本ならではの季節感が根付いたのだと思います。
まとめ
「読書の秋」という言葉には、ただの季節のキャッチコピー以上の歴史が隠れています。
ルーツは、唐の文人・韓愈が詠んだ「燈火親しむべし」という詩。秋は涼しく、夜が長いからこそ、本を読むのに最適な季節だと歌われたんです。
その考えはやがて日本にも伝わり、夏目漱石の『三四郎』に引用されたことで文学の中でも広まりました。さらに戦後の1947年に「読書週間」が始まり、10月27日〜11月9日が毎年の恒例行事として続いてきたことで、「秋=読書の季節」というイメージが全国に定着したのです。
だからこそ、紅葉の季節に本を手に取ることには特別な意味があります。秋の静かな夜、灯りの下でページをめくれば、千年以上前から人々が大切にしてきた「心を整える時間」を、今の私たちも共有できるのです。
おすすめの本はこちら👉社会人におすすめの読みやすい本3選